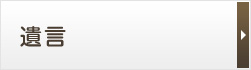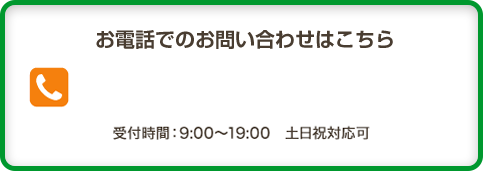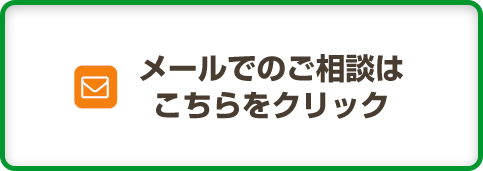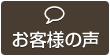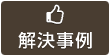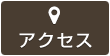【司法書士が徹底解説】兄弟相続とは?揉めないための対策と手続き完全ガイド - 専門家による無料相談受付中!
「もしもの時、自分の相続財産はどう兄弟間で分けられるのだろう?」
相続は避けて通れない人生の大切な節目です。
特に兄弟間での相続は、感情や法的な問題が絡み合い、煩雑になるケースが少なくありません。
しかし、知識があれば未然に問題を防ぐことも可能です。
この記事では、司法書士・行政書士の専門家としての視点から、
兄弟相続の基本から、遺産分割方法、相続税、相続放棄、そしてよくあるトラブルとその対策まで、兄弟相続にまつわる全てを徹底解説します。
あなたが円満な相続を実現するための一助となれば幸いです。
Contents
兄弟相続の基本と注意点をわかりやすく解説
兄弟相続は、親族間の複雑な感情や法律が絡み合い、しばしばトラブルの原因となります。
ここでは、兄弟相続の基本を理解し、注意すべき点について解説します。
円満な相続を実現するために、まずは基本的な知識を身につけましょう。
兄弟相続とは?誰が相続人になるのか
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、法律で定められた親族(相続人)が引き継ぐことです。
通常、相続順位は、配偶者、子供、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹の順で決まります。
しかし、兄弟のみが相続人になるのは、被相続人に配偶者、子供、直系尊属がいない場合に限られます。
例えば、被相続人が独身で、両親もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
この場合、兄弟姉妹は遺産を相続する権利を持つことになります。
兄弟姉妹が相続人になるケースは、意外と多いことを知っておきましょう。
兄弟のみが相続人になるケースとは?
兄弟のみが相続人となるケースは、具体的にどのような状況でしょうか。
以下のケースが考えられます。
・被相続人が生涯独身であった場合
・被相続人に子供がおらず、両親(または祖父母)がすでに他界している場合
・被相続人が離婚しており、子供がおらず、両親(または祖父母)がすでに他界している場合
これらのケースでは、兄弟姉妹が唯一の法定相続人となり、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議では、誰がどの財産をどれだけ相続するかを兄弟間で話し合い、合意する必要があります。
兄弟相続における法定相続分
遺言書がない場合、兄弟相続における法定相続分は、原則として以下のようになります。
| 相続人の構成 | 法定相続分 |
|---|---|
| 兄弟姉妹のみ | 均等に分割 |
| 兄弟姉妹と配偶者 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4を均等に分割 |
例えば、兄弟が2人の場合、遺産は均等に2分の1ずつ分割されます。
しかし、配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟で均等に分割します。
ただし、これはあくまで法律で定められた原則であり、兄弟間の合意があれば、異なる割合で遺産を分割することも可能です。
遺産分割協議を通じて、それぞれの事情や希望を考慮した上で、柔軟な遺産分割を目指しましょう。
次項では、具体的な遺産分割の方法について、話し合い(遺産分割協議)、調停、審判という3つの段階に分けて解説していきます。
【ケース別】兄弟相続の遺産分割方法:話し合い、調停、裁判、審判
兄弟相続における遺産分割の方法は、大きく分けて「遺産分割協議」「遺産分割調停」「遺産分割審判」の3つがあります。
それぞれの方法には特徴があり、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。
遺産分割協議:兄弟間で合意を目指す
遺産分割協議は、相続人である兄弟全員で話し合い、遺産の分け方を決定する方法です。
相続人全員の合意が必要であり、もっとも円満な解決を目指せる手段と言えるでしょう。
しかし、兄弟間の意見が対立すると、協議が難航する可能性もあります。
遺産分割協議を行う際には、以下の点に注意しましょう。
・相続財産の確定: 預貯金、不動産、有価証券など、全ての相続財産を明確にリストアップします。
・各相続人の法定相続分の確認: 誰が、どのくらいの割合で相続する権利があるのかを把握します。
・特別受益・寄与分の考慮: 特定の兄弟が被相続人から生前贈与を受けていた場合(特別受益)や、被相続人の財産形成に貢献した場合(寄与分)は、遺産分割の際に考慮する必要があります。
・合意内容の書面化: 口頭での合意だけでなく、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印することで、後々のトラブルを防止できます。
遺産分割協議がまとまらない場合は、専門家に相談することも検討しましょう。
遺産分割調停:家庭裁判所での話し合い
遺産分割調停は、遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所を介して話し合いを行う手続きです。
調停委員が間に入り、中立的な立場で助言や提案を行うことで、合意形成をサポートします。
遺産分割調停は、裁判所という公的な場で話し合いを行うため、冷静さを保ちやすく、感情的な対立を避けられるというメリットがあります。
しかし、あくまで話し合いの手続きであるため、相続人全員が合意しなければ、調停は不成立となります。
遺産分割調停を申し立てる際には、以下の書類が必要となります。
・調停申立書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続財産に関する資料(不動産の登記簿謄本、預貯金通帳のコピーなど)
調停が成立した場合、調停調書が作成され、これは確定判決と同等の効力を持ちます。
遺産分割審判:裁判所が遺産分割方法を決定
遺産分割審判は、遺産分割調停が不成立となった場合に、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定する手続きです。
裁判所は、民法に定められた相続の原則や、各相続人の事情などを考慮し、公平な遺産分割を行います。
遺産分割審判は、当事者の合意がなくても、裁判所の判断によって遺産分割が決定されるため、最終的な解決手段となります。
しかし、審判の結果に不服がある場合は、高等裁判所に控訴することができます。
遺産分割審判では、以下のような点が考慮されます。
・相続財産の評価: 不動産などの評価額が争点となる場合があります。
・特別受益・寄与分の有無と金額: 特別受益や寄与分が認められるかどうか、またその金額が争点となる場合があります。
・各相続人の生活状況: 各相続人の年齢、職業、収入、健康状態などが考慮されます。
遺産分割審判は、法的な知識や証拠が必要となるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
兄弟相続でよくあるトラブル事例と解決策:揉めないための対策
兄弟相続は、家族構成や財産状況によって様々なトラブルが発生しやすいものです。
ここでは、よくあるトラブル事例とその解決策、そして揉めないための対策を解説します。
トラブル事例1:遺産分割協議がまとまらない
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
兄弟間で意見が対立し、協議がまとまらないケースは非常に多いです。
特に、以下のような場合に協議が難航する傾向があります。
・相続財産の評価額で意見が異なる場合:不動産や株式などの評価額は、相続人の間で解釈が分かれることがあります。
・誰がどの財産を相続するかで意見が対立する場合:実家を誰が相続するか、預貯金をどのように分けるかなど、具体的な分割方法で意見が衝突することがあります。
・一部の兄弟が強硬な主張をする場合:特定の兄弟が自己の利益を優先し、他の兄弟の意見を聞き入れない場合、協議は停滞します。
【解決策】
・専門家(司法書士・弁護士など)に相談する:中立的な立場でアドバイスや交渉の仲介を依頼することで、冷静な話し合いを促進できます。
・不動産鑑定士などの専門家に評価を依頼する:客観的な評価額を提示することで、評価額に関する争いを解消できます。
・遺産分割調停を申し立てる:家庭裁判所の調停委員が間に入り、話し合いをサポートしてくれます。
トラブル事例2:特別受益・寄与分の主張が対立
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。
例えば、学費の援助や住宅購入資金の贈与などが該当します。
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に認められる取り分のことです。
例えば、被相続人の介護を長年行った場合などが該当します。
兄弟間で、これらの特別受益や寄与分の主張が対立すると、遺産分割協議は紛糾します。
【解決策】
・証拠を収集する:特別受益や寄与分を主張する側は、それを裏付ける客観的な証拠(領収書、預金通帳、介護記録など)を収集する必要があります。
・専門家に相談する:法的な根拠に基づいたアドバイスを受け、主張の妥当性を判断してもらいましょう。
・遺産分割調停・審判を申し立てる:家庭裁判所が証拠に基づいて判断し、特別受益や寄与分の額を決定します。
トラブル事例3:兄弟間の感情的な対立
相続は、単なる財産分与の問題ではなく、家族間の感情が複雑に絡み合う問題です。
過去の確執や不満が表面化し、感情的な対立から遺産分割協議が難航するケースも少なくありません。
【解決策】
・冷静な話し合いを心がける:感情的にならず、相手の意見を尊重する姿勢が大切です。
・第三者(親戚、友人など)に仲介を依頼する:当事者同士では感情的になりやすい場合、信頼できる第三者に間に入ってもらうことで、冷静な話し合いができることがあります。
・専門家(司法書士など)に依頼する:感情的な対立が激しい場合は、専門家が冷静な交渉を行い、円満な解決を目指します。
揉めないための対策:遺言書の活用、専門家への相談
兄弟相続で揉めないためには、事前の対策が非常に重要です。
対策1:遺言書の作成
被相続人が遺言書を作成し、財産の分け方を明確に指定しておくことで、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。
遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、法的に有効な遺言書を作成するためには、専門家(司法書士、弁護士など)に相談することをおすすめします。
| 詳細 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 被相続人が財産の分け方を指定 | 相続人間の争いを未然に防げる | 遺言書の内容によっては、相続人の不満が生じる可能性も |
対策2:専門家への相談
相続が発生する前から、専門家に相談しておくことで、相続に関する様々な疑問や不安を解消できます。専門家が中立な立場で円満な相続の実現をサポートできます。
| 詳細 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 相続に関する疑問や不安を解消、交渉の代行 | 法的な知識に基づいた解決が可能 | 費用がかかる |
兄弟相続は、感情的な問題や法的な問題が複雑に絡み合い、解決が難しいケースも少なくありません。
しかし、事前の対策と専門家への相談によって、円満な解決を目指すことができます。
相続問題でお悩みの場合は、早めに専門家にご相談ください。
兄弟相続の相続税:計算方法、2割加算、基礎控除を徹底解説
相続税は、相続財産の総額に応じて課税される税金です。
兄弟相続の場合も、相続税の計算が必要になる場合があります。
ここでは、相続税の計算方法、兄弟相続における2割加算、基礎控除について詳しく解説します。
相続税の計算方法:基礎控除額の算出
相続税の計算は、以下の手順で行います。
1.課税対象となる財産の価額を計算する:不動産、預貯金、有価証券など、相続財産を評価し、合計額を算出します。
2.基礎控除額を計算する:相続税には基礎控除があり、以下の計算式で算出します。
・基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
(法定相続人の数が多いほど、基礎控除額は大きくなります)
3.課税遺産総額を計算する:課税対象となる財産の価額から基礎控除額を差し引いたものが、課税遺産総額となります。
・課税遺産総額 = 課税対象となる財産の価額 − 基礎控除額
4.相続税の総額を計算する:課税遺産総額を法定相続分で按分し、各相続人の取得金額に応じた税率を掛けて相続税額を計算します。税率は、取得金額に応じて段階的に高くなります。
5.各相続人の納付税額を計算する:相続税の総額を、各相続人が実際に取得した財産の割合に応じて按分し、各相続人の納付税額を計算します。
| 計算項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税対象財産 | 不動産、預貯金、有価証券など |
| 基礎控除額 | 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) |
| 課税遺産総額 | 課税対象財産 – 基礎控除額 |
| 相続税の総額 | 課税遺産総額を法定相続分で按分し、税率を乗じる |
| 各相続人の納付税額 | 相続税の総額を、各相続人の取得割合に応じて按分 |
兄弟相続における相続税の2割加算とは?
兄弟が相続人となる場合、相続税額が2割加算されるケースがあります。
これは、被相続人の配偶者、父母、子供以外の人が相続する場合に適用されるものです。
兄弟は被相続人から見て「二親等の血族」にあたりますが、2割加算の対象となるため注意が必要です。
兄弟姉妹は被相続人とは横のつながりであり、親や子などの縦のつながりに比べて、相続税のうえでは不利となることが多いです。
例えば、相続税額が2,300万円と計算された場合、2割加算されると460万円が加算され、2,760万円が相続税額となります。
これは大きな負担となるため、事前に把握しておくことが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2割加算の対象者 | 被相続人の配偶者、父母、子供以外の人(兄弟姉妹、甥、姪など) |
| 計算方法 | 相続税額 × 0.2 |
相続税の申告と納税
相続税の申告と納税は、相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)から10ヶ月以内に行う必要があります。
申告期限までに申告・納税を行わない場合、延滞税や加算税が課される可能性がありますので、注意が必要です。
相続税の申告は、税務署に申告書を提出して行います。
申告書には、相続財産の明細や評価額、相続人の情報などを記載する必要があります。
必要書類を揃え、正確に記載することが重要です。 相続税の納税は、原則として現金一括納付となります。
しかし、相続財産に不動産が多く、現金が不足している場合には、延納や物納といった制度を利用できる場合があります。
これらの制度を利用するには、一定の要件を満たす必要があり、税務署への申請が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告期限 | 相続開始を知った日から10ヶ月以内 |
| 申告先 | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 納税方法 | 原則として現金一括納付、延納・物納も可能 |
兄弟相続の相続放棄:手続き、必要書類、期限、注意点
相続が発生した際、必ずしも財産を全て受け継がなければならないわけではありません。
もし、被相続人(亡くなった方)に多額の借金があった場合など、相続したくない事情がある場合は「相続放棄」という選択肢があります。
ここでは、兄弟相続における相続放棄について、その手続き、必要書類、期限、注意点を詳しく解説します。
相続放棄とは?メリット・デメリット
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないという法的な手続きです。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄は、借金などのマイナスの財産が多い場合に有効な手段ですが、同時にプラスの財産(預貯金、不動産など)も相続できなくなるという点に注意が必要です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 借金などのマイナスの財産を相続しなくて済む | プラスの財産(預貯金、不動産など)も相続できなくなる |
| 相続に関するトラブルから解放される | 後順位の相続人に相続権が移る場合がある |
| 特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合に、他の相続人が相続放棄することで遺産分割協議がスムーズに進む場合がある | 相続放棄の撤回は原則として認められない |
相続放棄の手続きと必要書類
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。
必要な書類は以下の通りです(一般例)。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 相続放棄の申述書 | 家庭裁判所のウェブサイトからダウンロード可能 |
| 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本) | 出生から死亡までの連続したもの |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | – |
| 申述人の戸籍謄本 | – |
| (申述人が被相続人の兄弟姉妹の場合)被相続人の父母の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本) | – |
| (申述人が被相続人の兄弟姉妹の場合)被相続人に子(またはその代襲者)がいないことのわかる戸籍謄本 | – |
| 収入印紙 | 800円(申述人1人あたり) |
| 郵便切手 | 家庭裁判所によって金額が異なるため、事前に確認が必要 |
※上記は一般的な必要書類であり、個別のケースによって異なる場合があります。詳しくは、「無料相談」にてご回答いたします。
相続放棄の手続きはご自身で行うことも可能ですが、書類の準備や手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続放棄の期限と注意点
相続放棄には、原則として「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」という期限があります。
この期間を過ぎてしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
この期間を「熟慮期間」といいます。
ただし、被相続人の財産状況が不明な場合など、特別な事情がある場合は、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を延長できる場合があります。
熟慮期間の延長を希望する場合は、早めに専門家にご相談ください。
また、相続財産を一部でも処分してしまうと、相続放棄ができなくなる場合があります。
例えば、被相続人の預金を引き出して使用したり、不動産を売却したりすると、相続を承認したとみなされる可能性がありますのでご注意ください。
相続放棄は、一度行うと原則として撤回できません。
そのため、相続放棄をするかどうかは、慎重に判断する必要があります。
財産状況を十分に調査し、専門家にも相談した上で、後悔のない選択をしましょう。
【Q&A】兄弟相続でよくある質問:税金、手続き、遺産分割
Q1:兄弟の一人が認知症の場合、遺産分割はどうなる?
A. 兄弟の一人が認知症の場合、その兄弟は遺産分割協議に参加することができません。
なぜなら、遺産分割協議は、相続人全員が遺産について自由に意思決定できることが前提だからです。
認知症の程度によっては、判断能力が十分でないとみなされ、法的に有効な意思表示ができないと判断される可能性があります。
このような場合、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任してもらうことで、認知症の兄弟の代わりに遺産分割協議に参加してもらうことができます。
成年後見人は、認知症の方の財産管理や法律行為を代行する役割を担い、本人の利益を最大限に考慮して遺産分割協議を進めます。
成年後見制度には、後見、保佐、補助の3種類があり、認知症の程度によって適切な制度を選択する必要があります。
司法書士や弁護士などの専門家に相談し、最適な方法を選択することをオススメします。
Q2:疎遠な兄弟がいる場合の遺産分割協議はどう進める?
A. 疎遠な兄弟がいる場合、遺産分割協議を進めるのは難しいと感じるかもしれません。
しかし、相続手続きを進めるためには、必ず遺産分割協議を行う必要があります。
まずは、疎遠な兄弟の連絡先を調べ、手紙や電話などで連絡を取ってみましょう。
数十年来疎遠だった兄弟と連絡を取り、遺産分割をスムーズに行った事例も存在します。
もし連絡先がわからない場合は、戸籍の附票を取得することで、現在の住所を調べることができる場合があります。
また、司法書士や弁護士などの専門家に依頼して、連絡を取ってもらうことも可能です。
遺産分割協議では、各相続人の法定相続分を尊重しつつ、お互いの事情を考慮しながら、合意を目指すことが大切です。
疎遠な兄弟との間で感情的な対立がある場合は、第三者である専門家を交えて話し合いを進めることで、円満な解決につながる可能性が高まります。
音信不通、疎遠になった相続人がいると、相続手続きが進まずに預貯金や不動産の手続きができないことがあります。
疎遠になった相続人との遺産分割を行う方法、注意点、遺産分割協議がまとまらないときの対策などを知っておきましょう。
Q3:遺産に不動産しかない場合、兄弟でどのように分割する?
A. 遺産に不動産しかない場合、兄弟で遺産分割を行う方法としては、主に以下の3つが考えられます。
・現物分割:不動産を物理的に分割する方法です。ただし、建物を分割したり、土地を細かく分筆したりする必要があるため、現実的には難しいケースが多いです。
・換価分割:不動産を売却し、売却代金を兄弟で分割する方法です。公平な分割が可能ですが、売却の手間や費用がかかること、また、売却益に対して税金がかかることに注意が必要です。
・代償分割:兄弟の一人が不動産を相続し、他の兄弟に相当する金額を支払う方法です。不動産を相続する人が資金を用意する必要がありますが、不動産を手放したくない場合に有効です。
どの方法を選択するかは、兄弟間の話し合いによって決定します。
不動産の評価額や、各兄弟の経済状況、希望などを考慮し、最適な方法を選択しましょう。
必要に応じて、不動産鑑定士に評価を依頼したり、税理士に税金について相談したりすることも検討しましょう。
Q4:相続税の納税資金がない場合はどうすればいい?
A. 相続税は、現金で一括納付することが原則ですが、納税資金がない場合は、以下の方法を検討することができます。
・延納:相続税を分割で納付する方法です。一定の要件を満たす必要がありますが、最長20年まで分割納付が可能です。
・物納:現金での納付が難しい場合に、相続した財産(不動産など)で相続税を納付する方法です。物納できる財産の種類や要件が厳しく定められています。
・相続税ローン:金融機関が提供する相続税納税のためのローンを利用する方法です。担保が必要となる場合があります。
・相続した財産の売却:相続した財産を売却し、納税資金を確保する方法です。換価分割と同様に、売却益に対して税金がかかることに注意が必要です。
どの方法を選択するかは、相続財産の種類や金額、各相続人の経済状況によって異なります。
税理士などの専門家に相談し、最適な方法を選択することをおすすめします。
まとめ|兄弟相続は専門家への相談が安心!円満な解決を目指しましょう
兄弟相続は、親族間の感情が複雑に絡み合い、遺産分割協議が難航するケースも少なくありません。
この記事では、兄弟相続における基本的な知識から、遺産分割の方法、よくあるトラブル事例とその解決策、相続税、相続放棄まで、幅広く解説しました。
しかし、個々の状況によって最適な解決策は異なり、法的な知識も必要となるため、ご自身だけで解決しようとすると、かえって事態を悪化させてしまう可能性もあります。
円満な相続を実現するためには、早い段階で専門家である司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、法的な知識に基づいて適切なアドバイスを提供し、遺産分割協議のサポート、調停や審判の手続き代行など、様々な面から相続をサポートしてくれます。
兄弟相続でお悩みの方は、ぜひ「平塚相続遺言相談センター」にご相談ください。
豊富な経験と実績に基づき、お客様一人ひとりの状況に合わせた解決策をご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
サポート料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では220,000円(税込)~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
| 相続財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 220,000円(税込) |
| 200万円を超え500万円以下 | 275,000円(税込) |
| 500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.32%+20.9万円(税込) |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+31.9万円(税込) |
| 1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64.9万円(税込) |
| 3億円以上 | 価額の0.44%+163.9万円(税込) |
兄弟間の相続手続きも当事務所にお任せ下さい!
当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
予約受付専用ダイヤルは0463-26-9171になります。お気軽にご連絡ください。
・電話受付 9:00~19:00(土・日・祝日・夜間も対応可能)
相続手続きは、人によって状況も違い、進めていく中でわからないことも多く出てきます。
また時間がない中、役所に出向いたり郵送手続きをしたりと、手続きが終わるまでにかなりの労力が必要です。
専門家にお任せしていただくと、煩わしい手続きから解放されるだけでなく、相続に関わるご不安を全て解消させていただきます。
相続手続きでお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士

平塚相続遺言相談センター
・代表:金子智明
・保有資格:司法書士、行政書士
・業務内容:相続登記、相続手続全般、相続放棄、遺産分割協議書、遺言書作成、家族信託に関するサポート
・経歴:平塚相続遺言相談センターの代表を勤める。
2012年に金子司法書士行政書士事務所を開業。
2023年に128名の行政書士を束ねる神奈川県行政書士会平塚支部の支部長に就任。
「相談者様のことを第一に考えたサポート」を目指し、気楽に何でも相談できる環境作りを心がける。
また、累計2,300件以上の豊富な相談経験と実績から相談者の信頼も厚い。







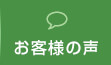



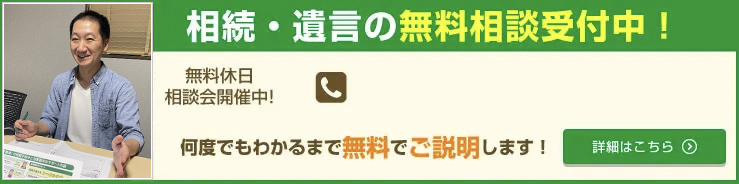
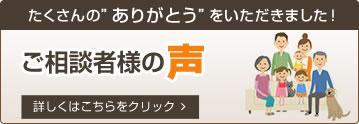
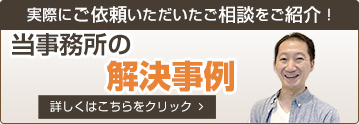
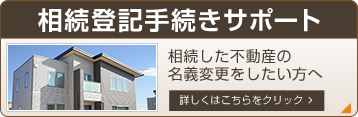
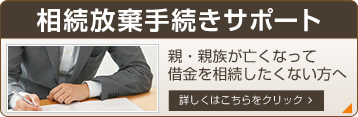
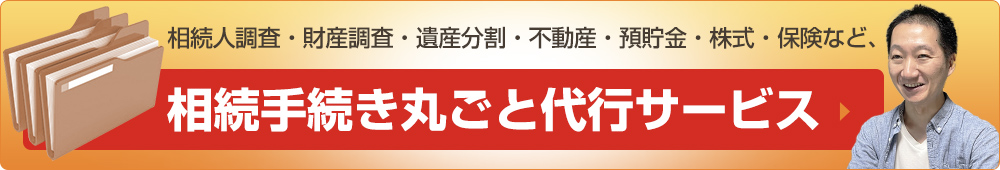
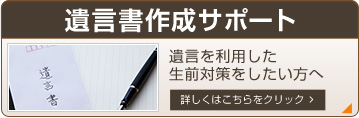
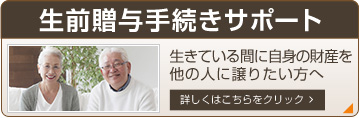


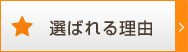
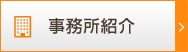



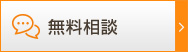


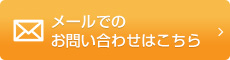

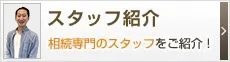


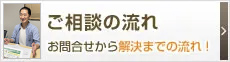

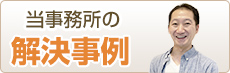

.png)

.png)
.png)